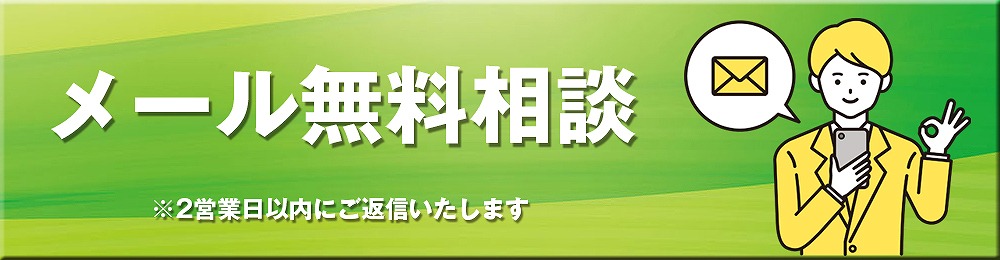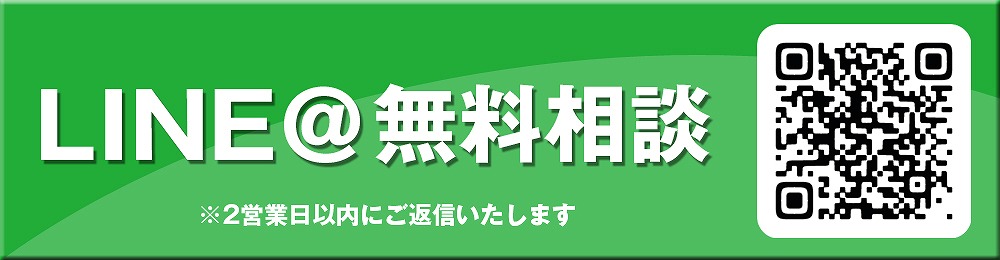家屋の侵入はトラブルを招きます



適切な対応をオススメします
目次
はじめに
愛知県では、都市部から郊外にかけて多くの住宅が害獣による被害を受けています。特に、近年では農地の減少や都市開発の進行に伴い、野生動物が人間の生活圏に入り込むケースが増加しています。害獣が家屋に侵入すると、屋根裏や壁の中で繁殖したり、配線をかじって火災の原因になったりするなど、大きなトラブルにつながる可能性があります。
愛知県において住宅へ侵入しやすい害獣として、以下のような動物が挙げられます。
- アライグマ:手先が器用で、屋根裏や床下に侵入しやすい。農作物だけでなく、家庭のゴミも荒らすことがある。
- ハクビシン:屋根裏に住み着きやすく、天井のシミや悪臭の原因となる。
- イタチ:細い隙間から侵入でき、家の中で悪臭の強い尿をまき散らすことがある。
- ネズミ:壁の中や天井裏に巣を作り、配線をかじることで火災を引き起こすことがある。
本記事では、愛知県における害獣の侵入経路を詳しく解説し、効果的な対策方法を紹介します。害獣の被害を防ぐためには、侵入経路を把握し、適切な対策を講じることが重要です。
害獣の主な侵入経路
屋根・屋根裏からの侵入
屋根は害獣が最も侵入しやすい経路の一つです。特に以下のような箇所から侵入が発生しやすいです。
- 屋根の隙間や瓦のずれ:台風や地震によって瓦がずれたり、老朽化で隙間ができたりすると、害獣が簡単に入り込む。
- 通気口・換気口からの侵入:屋根裏の換気口が破損していると、害獣が入り込む原因となる。
- 雨どいを伝って上がるケース:アライグマやハクビシンは雨どいを利用して屋根に登り、侵入を試みる。
壁の隙間・ひび割れ
壁の小さな隙間も害獣の侵入経路となります。特に以下の箇所は注意が必要です。
- 壁にできた亀裂や老朽化による隙間:築年数の古い家では、壁に亀裂が入りやすく、ネズミやイタチが侵入することがある。
- 外壁材の継ぎ目や劣化したコーキング部分:コーキングが劣化すると、小さな隙間ができ、害獣が侵入しやすくなる。
基礎部分や床下からの侵入
床下の隙間も害獣の侵入経路となります。
- 床下換気口の網の破損:金網が破損していると、ネズミやイタチが入り込む。
- 基礎コンクリートの割れ目:ひび割れから小動物が侵入することがある。
- 地面との隙間:基礎の下に空間があると、そこから侵入される可能性がある。
窓・ドア・換気扇まわり
- 網戸の破れ:ネズミや小動物は網戸の小さな穴からでも侵入することがある。
- ドアの隙間(特に引き戸やスライドドア):ドアの下に隙間があると、小動物が入り込む。
- 換気扇のダクト:フィルターが破損していると害獣が侵入する可能性がある。
ベランダ・庭・外構
- ベランダの隙間や排水口:排水口のカバーが外れていると、そこから害獣が侵入することがある。
- 庭の植栽を伝っての侵入:木の枝を伝って屋根や窓に侵入するケースがある。
- 物置やガレージから家の中へ:開けっ放しにしていると害獣が住み着くことがある。
害獣が侵入しやすい家の特徴
- 老朽化している家:壁や屋根の隙間が増え、侵入されやすい。
- 隙間の多い構造(通気性の良い古民家など):害獣が入り込みやすい構造の家は特に注意が必要。
- 周囲に緑が多い、川が近いなどの環境:害獣が生息しやすいエリアでは、侵入リスクが高まる。
害獣の侵入を防ぐための対策
侵入経路の封鎖
- 屋根や壁の隙間を点検・補修
- 床下や換気口に金網を設置
- 窓やドアの隙間を埋める
害獣を寄せ付けない環境づくり
- ゴミの管理:生ゴミやペットフードを放置しない。
- 庭の整理:雑草や不要な物を放置しない。
- 侵入防止グッズの活用:超音波装置、忌避剤の使用。
すでに侵入された場合の対応
- フンや足跡のチェック:害獣の侵入を早期発見する。
- 忌避剤やトラップの使用:市販の忌避剤を活用。
- 専門業者への相談:自己対応が難しい場合はプロに依頼。
まとめ
- 愛知県の害獣被害は住宅でも深刻化している。
- 侵入経路を理解し、早めの対策が重要。
- 専門家の力も借りつつ、被害を最小限に抑えよう。
害獣の侵入を防ぐためには、日頃の点検と対策が不可欠です。安全で快適な住環境を守るため、早めの対策を心がけましょう。